恋川春町は江戸時代中期、駿河小島藩に仕える武士でした。
また、浮世絵師でもあり、洒落本・狂歌などの文章も書ける歔作者でもありました。
「恋川春町」の可愛らしい名前の由来が気になりますね。本名なのでしょうか。
30歳の頃に制作した『金々先生栄花夢(きんきんせんせいえいがのゆめ)』。
大人向けの読み物「黄表紙」というジャンルの始まりとされています。
この記事では、以下のことについてご紹介していきます。
•恋川春町の名前の由来は?
•江戸の町民に愛された「黄表紙」とは?
•恋川春町の『金々先生栄花夢』が大ヒット!
•恋川春町を演じるのは岡山天音
恋川春町の名前の由来は?
恋川春町(こいかわ・はるまち)とは、江戸時代中期、駿河国小島藩の武士・倉橋格(くらはし・いたる)のことです。
倉橋格が小説を書く際のペンネームに使っていたのが、恋川春町になります。
小島藩の江戸藩邸が小石川春日町の「春町」にあったことと、
浮世絵師・勝川春章の名前から「川」と「春」を借用したと言われています。
「恋川春町」。
とても綺麗なペンネームに
「女性なの?」「性別はどっち?」と思われる方も多いようですね。
「べらぼう」に勝川春章が登場ということは?
「べらぼう」に勝川春章が登場に、どのような意味があるのでしょう。
勝川春章は、若き日の葛飾北斎が最初に師匠と仰いだ人といわれています。
北斎は、勝川春章に入門後に「勝川春朗」と名乗り青年時代を活動していました。
勝川春章の存在なくして、北斎などの浮世絵師が世にでることはなかったといえる重要な人物です。
「べらぼう」では、勝川春章役を前野朋哉さんが演じます。
\ #大河べらぼう 新キャスト/
— 大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」日曜夜8時 (@berabou_nhk) August 27, 2024
◤ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
勝川春章役 #前野朋哉
葛飾北斎の師匠で
当代一の役者絵師
____________◢https://t.co/sLfyjEuYEC
コメント全文&役柄について詳しくは👆
大河ドラマ
べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~ pic.twitter.com/cemTvqc2n7
江戸の町民に愛された「黄表紙」とは?
「黄表紙」とは?、その名の通り黄色い表紙をまとう絵入りの読み物のこと。
「べらぼう」の舞台である江戸時代中期に流行した、知的でユーモアたっぷりのストーリーが展開する、大人向けの読み物です。
1775年(安永4年)に刊行された恋川春町の『金々先生栄花夢』が最初の黄表紙といわれています。
それまでの子供向けの草双紙とは一線を画してアダルトな要素も盛り込まれた物語に。
表紙の色がそのままネーミングとなるパターンは、
現代における大学受験生の「赤本」と同じですね。
恋川春町の『金々先生栄花夢』が大ヒット!
恋川春町が創作した『金々先生栄花夢』を世出出したのは、蔦重ではなくて、「べらぼう」で片岡愛之助さん演じる鱗形屋孫兵衛。
金村屋金兵衛という田舎の若者が夢見たお話。
一旗揚げようと江戸に出てきた金兵衛が目黒不動でうとうとしている間に、
「大金持ちになったが散財して元の無一文になる」という夢を見て
そのはかなさを悟り、田舎に戻っていくというストーリーです。
ちなみに「金々先生」とは当時の流行語で、金持ちで粋な人のこと。
後に、文政(1818年~1831年)の頃になると、
「今より見れば、さほどおもしろきものでもなし」と残念な評価となっているようですが…
恋川春町は松平定信の改革で処罰
恋川春町が次々と黄表紙で作品を発表して喝采を浴びたのは、田沼意次が幕府の実権を握っていた「田沼時代」。
田沼意次が失脚すると、松平定信による寛政の改革が行われることに。
世の中は、風紀を乱す行為を取り締まる空気が流れます。
その時代の中1788年(天明8年)に刊行された『鸚鵡返文武二道(おうむがえしぶんぶのふたみち)』。
その内容が、幕府の政策を批判していると松平定信の耳に届き、恋川春町は定信から呼び出しを受けますが、春町は病気を理由に断りました。
しかし、幕府の命で『鸚鵡返文武二道』は絶版となり、その年恋川春町こと倉橋格は息を引き取りました。
恋川春町は大学入試の問題に登場!
一般的な知名度ではそれほど高くありませんが、
恋川春町は大学入試の日本史で取り上げられるケースもあります。
- Q「寛政の改革で弾圧を受けた黄表紙作家の恋川春町の作品は次のうちどれですか」
四択問題で答えなさい。 - A
正解は「金々先生栄花夢」を選択
例えば、こんな感じで江戸三大改革の1つである寛政の改革と、江戸中期の文化を絡めた出題があるようです。
恋川春町を演じるのは岡山天音
恋川春町を演じる岡山天音さんは、今回の役柄について、
\ #大河べらぼう 新キャスト/
— 大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」日曜夜8時 (@berabou_nhk) January 11, 2025
◤ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
倉橋格/恋川春町 #岡山天音
喜三二の親友で 黄表紙の傑作
『金々先生栄花夢』の作者
____________◢https://t.co/z07qdaaLCZ
新キャストはあと8人!詳しくは👆 pic.twitter.com/0lmplgGEJd
岡山天音さんは、「何度も心を揺さぶられました」と語っています。
現在放送中の大河ドラマ「べらぼう」にも、これから登場する予定となっています。
まとめ
恋川春町は江戸時代中期、駿河小島藩に仕える武士でしたが、浮世絵師でもあり、洒落本・狂歌などの文章も書ける歔作者でもありました。
「恋川春町」の名前の由来は、小島藩が小石川春日町にあり、浮世絵師・勝川春章の名前から「川」と「春」を借用したと言われています。
30歳の頃に制作した『金々先生栄花夢』は、大人向けの読み物「黄表紙」の始まりとされています。
「何度も心を揺さぶられました」と語る、恋川春町を演じる岡山天音さんの演技に注目です。
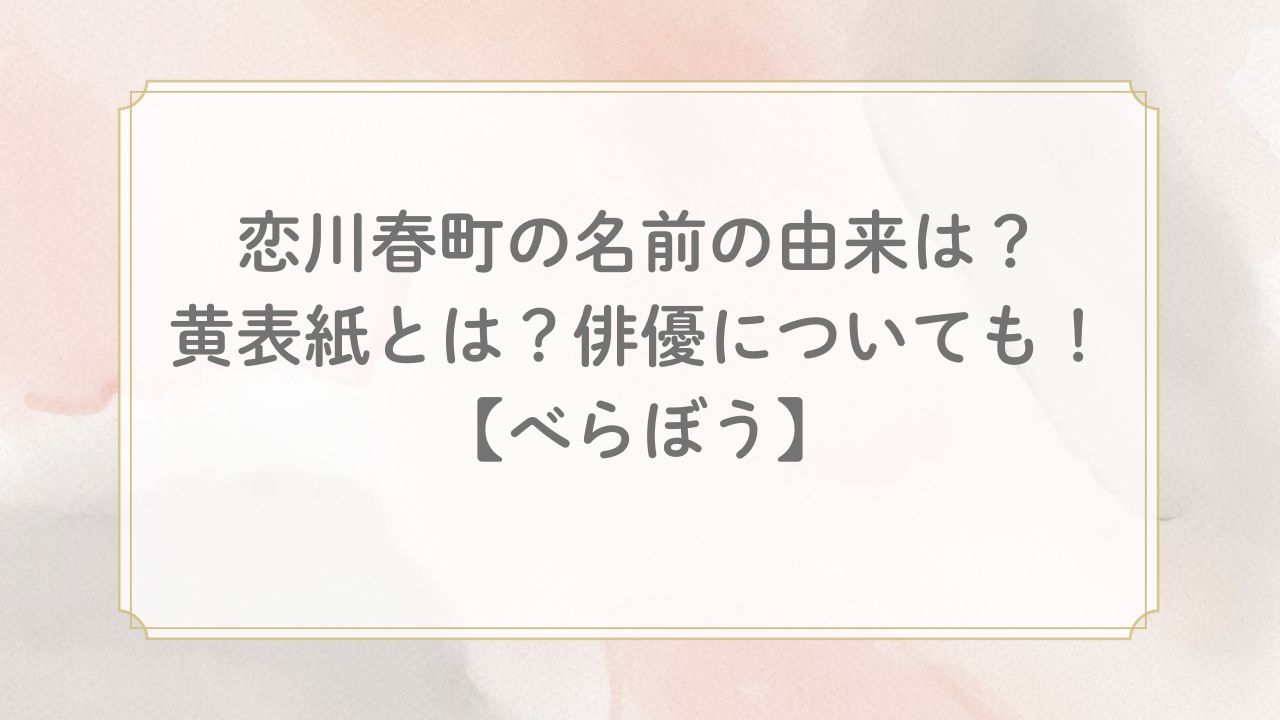
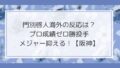
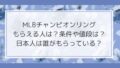
コメント